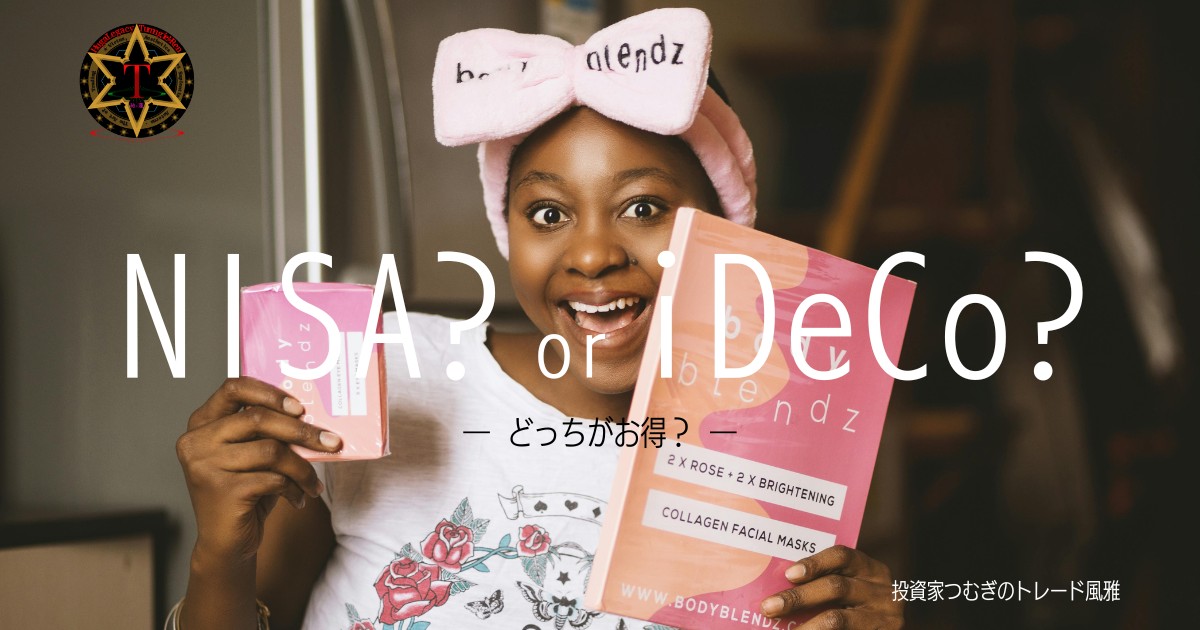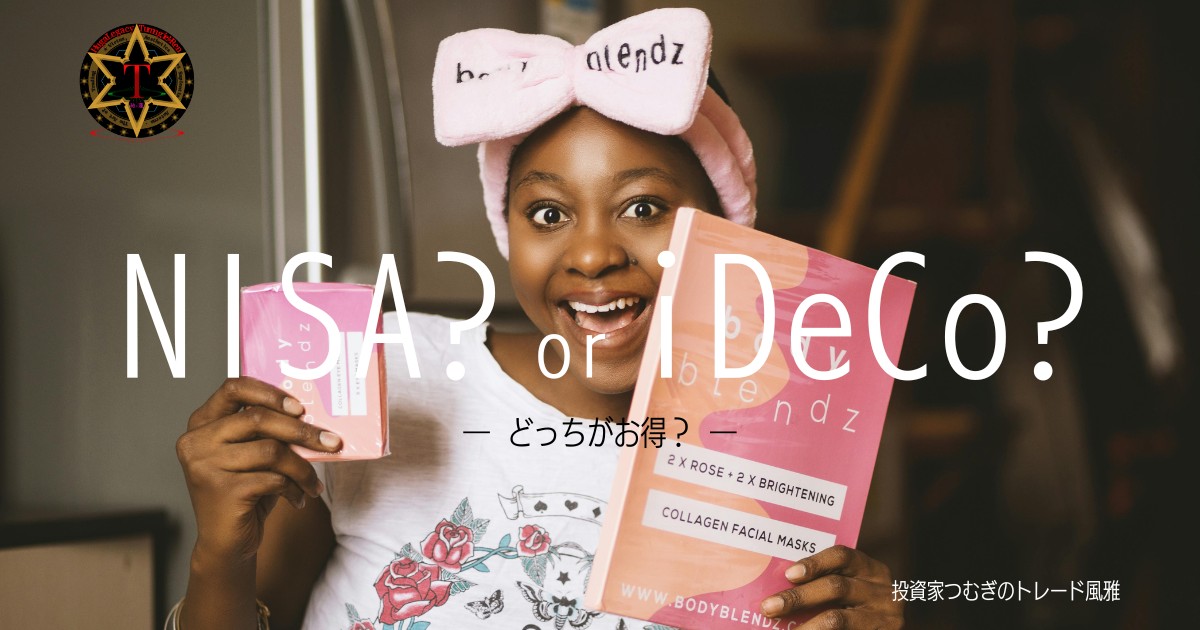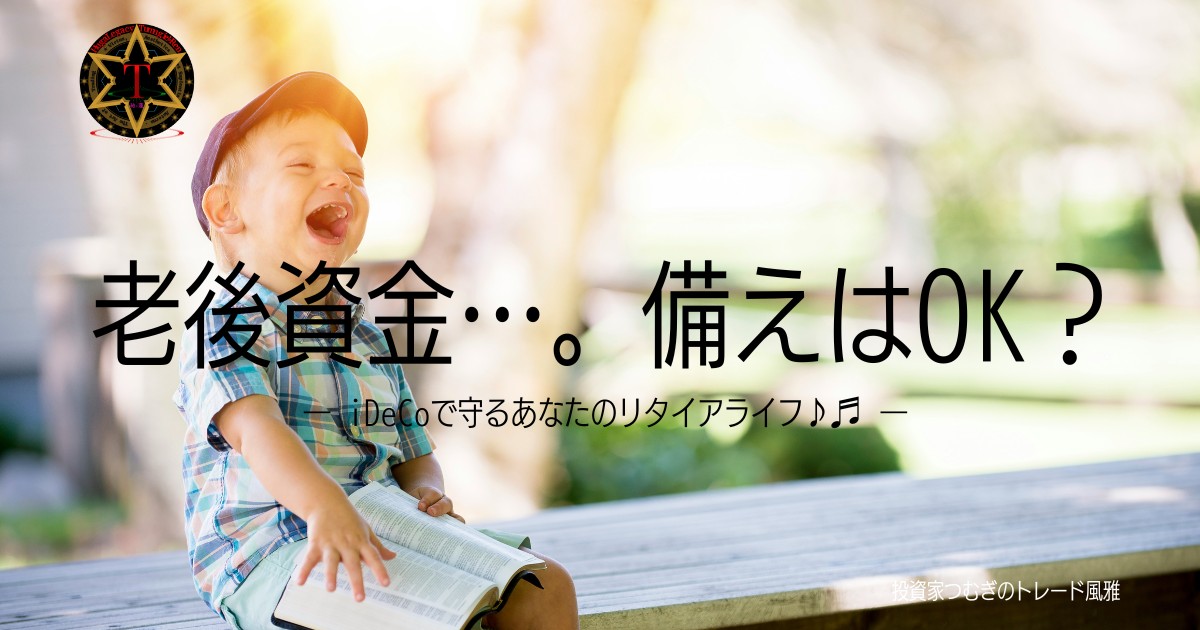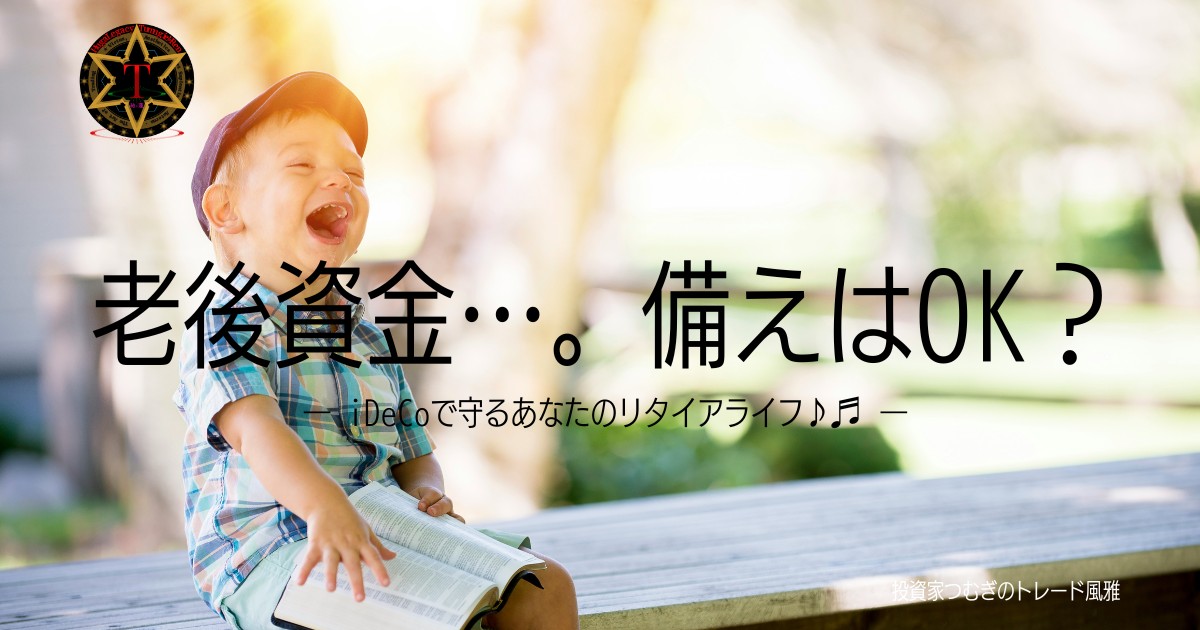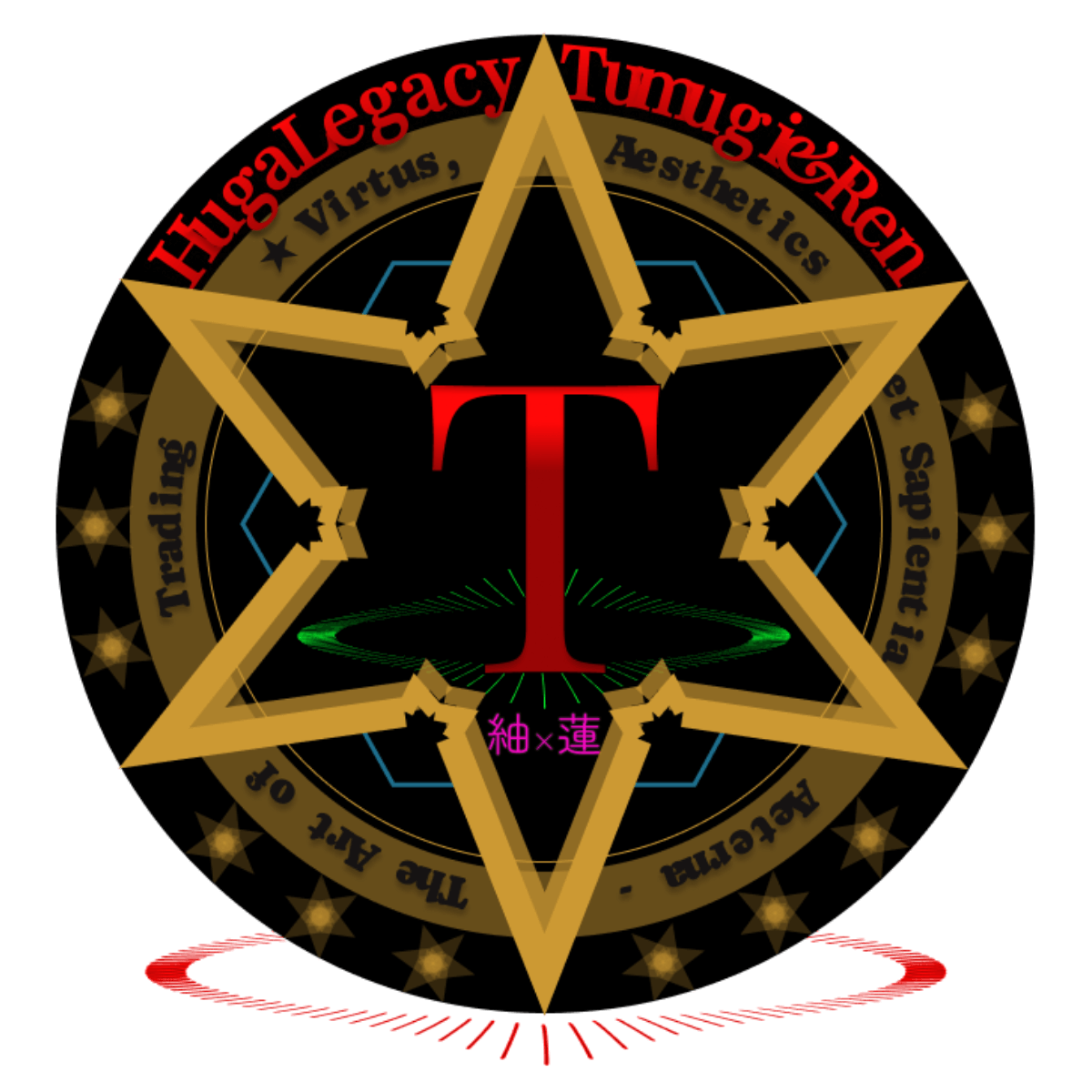つむぎ
つむぎこんにちは!風雅なスイング投資家のつむぎです!
ようこそ「つむトレ」へ



こんにちは!つむぎのアシスタントのレンです!
「もう50代だから遅いかな?」
「60代から老後資金は間に合わない?」
そんなふうに思ってる人って、
案外多いんじゃない?
実はそれ、半分は“思い込み”なんだよね。
たしかに老後の資金づくりって、若いうちからコツコツ始めるが王道。
だけど50代・60代には、50代・60代だからこそ出来る戦い方がある。
人生100年時代…。
むしろ、子育てがひと段落したこの50代・60代から、 老後資金をつくり始めるのがふつうなくらいだよ。
だから「もう遅い」なんて言うのは嘘。
ぜんぜん、大丈夫!
じゃあ、そのカギは何か?
そう──「iDeCo」と「NISA」。
似てるようでちょっと違う、この2つの非課税制度をどう組み合わせるかで、未来のお金の安心度は大きく変わってくる。
「iDeCoで固めて、NISAで伸ばす」
この順番こそ、
つむぎ流の老後マネープラン♪



本日の風雅なトレードテーマはコレ!



じゃじゃーん!
iDeCoで固めてNISAで伸ばす老後マネー♪
今回は「50代・60代のための資産形成」をテーマに、“NISA+iDeCo”を活用したつむぎ流50代・60代から始める資産形成術を、やさしく解説していくよ。
焦らず、惑わされず──
“強制貯蓄+節税+複利”の力を味方につけて、老後の安心を組み立てていこう。
50代・60代から始めるつむぎ流NISA&iDeCoの資産形成術
「年金だけで暮らせるのかな?」
「退職金も減ってるって聞くし…」
「老後2,000万円問題って、本当なの?」
50代・60代がひそかに感じているのは、やっぱり老後資金の不安…。
- 年金の受給開始が65歳以降にずれ込む現実
- 退職金制度の縮小
- 企業年金の減額傾向
- 平均寿命の伸びで「老後30年以上」という長い生活期間
年金だけじゃ生活費が足りないよね。
50代・60代からでも、将来に向けて自分の資産をしっかり増やす工夫をしておくのが、逆転資産形成のカギになる。



なんか、聞いているだけで焦ってくるな…。



ま、そこは安心して。
焦る気持ちはみんな一緒!
ちゃんと解決策、用意してるから♪
ここで大事なのは「不安を直視すること」。
「なんとなく大丈夫」と思って何もしないのが一番のリスク。
50代・60代が抱えるリアルな将来・老後資金の悩み
「老後資金、このままで本当に足りる?」
50代・60代の多くが心のどこかで感じているこの不安、実際の調査データにもはっきり出ているよ。
不安①:年金・公的補助だけでは不十分という見通し



年金だけで生活できるのか不安なんだけど…



そうだよね~、
その悩み、実は多くの人が同じことを思ってる…
- 生命保険文化センターの調査では、老後の不安で最も多いのが「公的年金だけでは不十分」で79.4%。
- 「退職金や企業年金だけでは足りない」と答えた人も31.4%。
- 結果、「老後の生活に不安」と答えた人が82.2%と大半を占めている。
🔗 参考リンク
👉 公益財団法人 生命保険文化センター「生活保障に関する調査(2022年)」
年金や退職金だけに頼るのは、やっぱり不安が多いって共通認識になっているよ。
不安②:健康・介護・物価上昇への懸念
- コスモラボのシニア調査では、「健康面」(83.7%)が圧倒的で「介護・終活」(54.2%)と合わせて、回答者の約8割が「老後不安」を抱えていていると回答。
- また、「物価上昇」(63.3%)や「老後資金不足」(59.6%)も上位にランクイン。
🔗 参考リンク
👉 PR TIMES「生活を脅かす経済的不安」
年を取ると医療費が増えるのは当然だし、物価が上がると生活費もかさむ。
だから、この不安はかなりリアルな問題…。
不安③:資産枯渇・取り崩しリスク
- 高齢者の困りごとには、「老後資金の不足(資産が予定より早く枯渇する)」って心配する声もよく聞かれるよね。
- 実際、2019年の金融審議会の報告では、夫婦世帯で年金や勤労収入を除いた不足額は1,300~2,000万円という試算もある。
🔗 参考リンク
👉 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書



え、そんなに不足する可能性があるの…!?



そう。でも、適切な資産形成でこの取り崩しリスクは減らせるんだよ。
不安④:資産格差・金融資産の少ない人が多い現実
- NIRA報告では、高齢世帯で金融資産450万円未満が最も多く、資産十分層は少数派。
- 単身世帯では6割が450万円未満という分布も目立つ。
🔗 参考リンク
👉 NIRA総合研究開発機構「高齢者世帯の所得・資産の実態と今後の政策課題」
つまり、まずは「維持すること」が課題になっている人も多いんだよね。
不安⑤:老後不安はあっても行動できていない日本人の現実
- メットライフ生命調査では、老後の不安上位に「お金」「健康」「認知症」「介護」が並ぶ。
- また、この調査では老後に悲観的な女性と楽観的な男性の意識の差が浮き彫りになっているよ。
- 健康についても多くの人が意識しているけど、具体的な行動に結びついていないのが今の日本人のリアルな状況だね。
🔗 参考リンク
👉 メットライフ生命「老後を変える全国47都道府県大調査」
健康を損なうと資産形成の土台も揺らぐ。だから、体も心もお金もセットで考えるのが大事なんだよね。
50代・60代の金融資産保有額ってどれくらい?
資産形成の第一歩は、まず自分の立ち位置を知ること。50代・60代はどれくらい資産を持っているのか、リアルな数字を見てみよう。
50代・60代における金融資産の平均値と中央値(お金事情のリアル)
ソニーライフの記事(金融広報中央委員会「世論調査 令和5年」より)によると、金融資産を保有していない世帯も含めた場合、
- 50代の金融資産:
平均値 1,212万円、中央値 200万円 - 60代の金融資産:
平均値 1,862万円、中央値 530万円
平均値と中央値に大きな差があるのは、資産の偏りが大きいことを示しているってこと。つまり、老後にお金に困らない人と、困る人とで二極化していることを表しているってわけだね。



「中央値」って、具体的にはどういう意味?



中央値は「ちょうど真ん中の人の金額」だよ。
つまり、50代なら半分は200万円以下、半分は200万円以上ということ。
平均値だけだと高額資産の人に引っ張られてしまうから、現実的な目安としては中央値を見たほうがわかりやすいんだよ。
金融資産を保有している世帯50代・60代の資産分布
\ 50代・60代の金融資産分布 /
| 金融資産額 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 9.6% | 6.6% |
| 100~200万円未満 | 6.1% | 4.6% |
| 200~300万円未満 | 3.5% | 3.9% |
| 300~400万円未満 | 3.8% | 3.4% |
| 400~500万円未満 | 3.8% | 2.0% |
| 500~700万円未満 | 5.3% | 6.2% |
| 700~1,000万円未満 | 5.5% | 5.5% |
| 1,000~1,500万円未満 | 7.8% | 6.8% |
| 1,500~2,000万円未満 | 4.2% | 5.1% |
| 2,000~3,000万円未満 | 5.1% | 9.1% |
| 3,000万円以上 | 10.7% | 19.0% |
金融資産を保有している世帯における中央値未満でこの表を見たとき、50代の中央値200万未満だと約16%、60代の中央値530万に近い500万未満だと 約20% 。
2000万以上の金融資産保有している世代は、50代で約16%、60代で約28%。
つまり、老後の資金を十分持っている世帯と十分ではない世帯と二極化しているのが顕著に分かれていることが分かるよ。



へぇ、2000万以上持ってる人もちゃんといるんだ。
それでいて、中央値未満の人も結構多いんだね。



そう。だから、今回は中央値未満の世帯を対象に、「50代・60代からでも間に合う資産形成術」を提案していくってわけ♪
ソニーライフの資料では、年代別に金融資産を保有していない世帯も含めた中央値も公表されていて、よりリアルな資産状況がわかるよ。
\ 全世代の金融資産分布 /
| 世帯主の年齢 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 151万円 | 10万円 |
| 30歳代 | 599万円 | 130万円 |
| 40歳代 | 811万円 | 180万円 |
| 50歳代 | 1,212万円 | 200万円 |
| 60歳代 | 1,862万円 | 530万円 |
| 70歳代 | 1,683万円 | 650万円 |
この表は金融資産を保有していない世代も含めているから、よりリアルな数字。この表にさっきの中央値未満がどれくらいで比べてみると、50代で約16%、60代で約20%を占め、これが資産保有二極化の実態を明確に示しているってわけ。
しかも、この計算、あくまで50代・60代における中央値未満での計算。
老後2000万円問題の視点で見ると、50代で約84%、60代で約72%と大半の人が深刻な状態に置かれているってことになるよね。
🔗 参考リンク
👉 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査 令和5年」
👉 ソニーライフ「貯蓄の平均値・中央値はいくら?」
貯蓄状況から見える現実
- 50代・60代 の多くは、まだ老後資金の準備が十分ではない。
- 特に、中央値未満の世帯は将来に不安を抱えやすい。
- でも大丈夫。ここから “NISA+iDeCo” を活用して資産形成を始めれば、十分に挽回可能。



まずは自分の資産状況を知って、現実を受け止めることがスタートライン。



現実を知った上で、どう行動するかが勝負ってことだね。
貯金ゼロの老後を過ごす現実…
「貯金ゼロの老後って、どんな生活なの?」
漠然と不安を抱える50代・60代の皆さん、
ここでは現実の声と数字をもとに、老後資金ゼロのリアルを見てみよう。
実際の声から見る厳しい現実
ネット掲示板やアンケート、シニア向け調査を見ると、こんな声が聞こえてくるよ。
- 「年金だけじゃ家賃も光熱費もギリギリ。外食や旅行なんて夢のまた夢」(50代・女性)
- 「医療費がかさむと、毎月の生活費が赤字になる…」(60代・男性)
- 「貯金ゼロだと、突然の病気や事故で生活が崩れるのが怖い」(50代・男性)
- 「老後も働かなきゃいけないかもしれないと考えると、精神的にもつらい」(60代・女性)
🔗 参考リンク
👉 生活保険文化センター「老後の生活費はいくらくらい必要と考える?」



うわぁ、みんな結構リアルな声だね…。



そうだね。これは一部の声じゃなくて、実際に身近で起こっている今の日本のリアル。
生活のリアルなイメージ
貯金ゼロの老後では、こんな状況が待ち受けていることも。
- 日常生活:食費・光熱費・医療費で毎月ギリギリ
- 想定外の出費:家電の故障、病気・介護費で資金ショート
- 心理的負担:常にお金のことで頭がいっぱい、外出や趣味も制限
- 働き続ける必要性:体力や健康のリスクを抱えながら収入確保



これって、もはや
“サバイバル生活” だね。



もちろん年金や補助があるけど、生活に余裕はほとんどないのが現実。
なぜ今から行動すべきか
貯金ゼロの老後の厳しさを知ると、逆に見えてくることもあるよ。
50代・60代だからこそ、
始める頃合いの資産形成のチャンス!
ということ。
- 定年前で収入はまだ安定している
- 子育てや住宅ローンが落ち着き、支出も減る
- 投資経験や社会経験を活かして冷静に資産運用できる



なるほど、現実を知ると焦るけど、逆に “行動のタイミング” としては悪くないってことだね。



その通り。老後へ向けて資産形成を始めるなら、むしろ50代・60代こそが頃合い♪
老後資金づくりは50代・60代からでも十分に間に合う理由
「もう50代だし、老後資金なんて今さら…」
そう思う人もいるかも…。
でも、50代・60代だからこそ使える強みがちゃんとあるんだよね。
ここでは、その強みを具体的に見ていこう。
収入の安定感
定年前の50代はキャリアのピーク期。
給与水準も高めで、投資に回せるキャッシュフローは若い頃よりぐっと増えることが多いよ。



え、そんなに余裕あるの?



意外とね。平均的な給与水準や退職金を考えると、今からでも投資にまわせる金額は結構あるんだよ。
🔗 参考リンク
👉 DODA 年齢別「年代別に見る日本の平均年収」
👉 FCおそうじ革命「最新版の世代別年収データ!」
支出の落ち着き
子育てや住宅ローンなど「人生の三大支出」がひと段落して、家計に余裕が出やすいのもこの世代の強み。



確かに、子どもが独立したらお金の出どころ減るもんね。



そうそう。生活費の負担が減った分を資産形成に回せるでしょ。
経験値の蓄積
投資や社会情勢に触れてきた経験がある人なら、リスクを冷静に見極めやすいし、投資経験がなくても人生経験で政治や経済に触れてきた経験値の蓄積は、本人が思う以上に案外大きいもの♪
金融市場の動きに慌てず、戦略的に運用できるのも50代・60代のアドバンテージだよ。
人生100年時代の時間軸
60歳からでも20〜30年の投資期間は残されている。複利を活かすには十分な長さだし、今からでも資産形成のチャンスは大きい。



「もう遅い」んじゃなくて「今が現実的に動きやすい」ってこと?



そういうコト!
むしろ、若い頃より条件は揃ってると言えるよ。
「もう遅い!」
ではなく
「今だからできる!」
この発想の転換が、老後資金づくりのスタートラインになる。
50代・60代でも、収入・支出・経験・時間の4つの強みを活かせば、十分に資産形成は間に合うんだよ。
50代・60代から始めるつむぎ流資産形成術のすすめ
さあ、ここまでで「50代・60代でもまだ間に合う」とわかったね。
じゃあ具体的にどう動けばいいのか?
つむぎ流の秘訣は「非課税制度をフル活用して、効率よく資産を増やす」ことにあるよ。
iDeCoで“強制貯蓄+節税”を味方に
iDeCoは、自分で積み立てる年金制度。
掛け金は全額所得控除になり、税金を抑えながら将来に備えられるのが大きな魅力。



控除っていうのは…?



簡単に言うと「払う税金が減る」ってこと。月々の積立がそのまま節税になる。
- 50代からでも、掛け金の上限いっぱいまで積み立てれば、数年でまとまった資産に。
- 加えて、運用益も非課税だから、複利の効果もグッと高まる。
🔗 参考リンク
👉 iDeCo公式サイト
NISAで“資産を伸ばす”戦略
NISAは、運用益が非課税になる投資口座。
iDeCoで土台を固めたら、NISAで資産を増やすステップに進むのがつむぎ流。



でも、今からでも株とか投資信託って大丈夫?



50代・60代は “守り投資” の考え方を加えることでリスクを見極めやすくなるし、長期運用で複利も効きやすいよ。
- 成長性のある商品に分散投資すれば、短期間でも資産を伸ばすチャンスあり。
- NISAなら売却益も非課税だから、利益を丸ごと再投資できる。
🔗 参考リンク
👉 NISA公式サイト
つむぎ流の順番は“固めて伸ばす”
- iDeCoで強制的に貯蓄+節税
- NISAで資産を伸ばす
この順番がポイント。
まず安全な土台を作ってから、攻める
という順序が、つむぎ流の50代・60代に最適プラン♪



なるほど、順番を間違えるとリスクが大きくなるってことか。



そうそう。無理のない範囲で、かつ最大限に制度を活かすのが肝心だよ。
50代・60代からでも遅くない資産形成は、制度の活用+戦略的な順番が鍵。
- iDeCoで土台を固め
- NISAで資産を伸ばす
これだけで、老後資金の不安はグッと減らせられるよ。
「もう遅い」じゃなくて、
「今だからこそできる資産形成」
さあ、一歩を踏み出して、未来のお金を自分の味方にしよう。
50代・60代の資産形成の特徴とリスク管理
50代・60代から資産形成を考えるとき、若い世代とは違う「壁」と「武器」がある。
投資期間が短い…
でも収入・経験・時間の使い方で有利な点もある。
ここでは、この世代ならではの資産形成の特徴とリスク管理のポイントを見ていこう。
投資期間が短いからこそ「守りと攻め」のバランスが命
50代・60代は若い世代に比べて投資期間が短いから、リスクを取りすぎると痛手が大きくなる。ここでは、投資期間と守り・攻めの投資を整理してみよう。
投資期間の目安
- 50代から始める場合
・65歳までの投資期間 → 約5~15年
・70歳までの投資期間 → 約10~20年 - 60代から始める場合
・65歳までの投資期間 → 約1~5年
・70歳までの投資期間 → 約5~10年
※期間はあくまで目安。運用期間の長さに応じてリスク許容度を調整することが大切。
守りと攻めのバランス
- 守りの投資
・現金・預金:元本保証で安全性が高い
・国債・社債:安定的な利息収入を狙える - 攻めの投資
・株式・株式投資信託:値動きはあるが成長性がある
・ETF・リート:分散しながら市場全体の成長に乗る



こうやって整理するとパッと全体像が見えるね。



投資期間と守り・攻めを意識して組み合わせることで、短期間でも安全に資産形成できる戦略が立てられるんだよ。
攻めの投資資金はこう作る!50代・60代のための「守りの仕組み」活用術
老後資金を増やすには、まず投資の原資をどう確保するかがスタートライン。
「もう今さら貯金なんて増えないよ…」と思いがちだけど、実は国の制度や控除を上手く使えば、現金をひねり出す方法がある。
ここでは、50代・60代がすぐに使える「攻めの資産形成の前に知っておきたい守りの仕組み」を整理してみよう。
医療費控除で“戻ってきたお金”を投資の原資に!
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、確定申告で税金が戻ってくる制度。
病院代だけでなく、薬局で買った市販薬や通院の交通費も対象になるケースがあるから見逃せない。
戻ってきたお金は、そのまま生活費に消えるよりも、NISAやiDeCoの投資原資へ回すのが老後資金づくりの近道だよ。
🔗 参考リンク
👉 国税庁「医療費控除」
高額療養費制度で家計を守り、投資資金を崩さない
高額療養費制度は、1か月の医療費が高額になったときに、自己負担額を一定水準まで抑えてくれる制度。
例えば70歳未満・年収約370万〜770万円の人なら、自己負担は1か月で約9万円程度に収まる。
これによって「投資のために積み立てたお金」を医療費で崩さずに済むよ。
🔗 参考リンク
👉 厚生労働省「高額療養費制度」
介護保険給付で将来の出費を抑え、今の投資余力を確保
介護保険給付は、要介護認定を受けると、介護サービス費用の自己負担が1〜3割に抑えられる制度。
現役世代にはあまり実感がないけれど、将来の出費が制度で軽減される分、今から投資に回せる余力を確保できるんだよね。
つまり「将来の安心=今の投資余力」につながる仕組みとして押さえておきたい。
🔗 参考リンク
👉 厚生労働省「介護保険制度」
制度を使って「投資原資をひねり出す」ことが老後資金づくりの第一歩
- 医療費控除 → お金が戻る → 投資原資に回せる
- 高額療養費制度 → 突発医療費から家計を守り、投資を崩さない
- 介護保険給付 → 将来の出費を抑え、今の投資余力を増やす
攻めの資産形成に入る前に、こうした制度を押さえて“投資資金をひねり出す”のが50代・60代の勝ち筋なんだよ。
50代・60代世代は、この3つの制度を知っておくだけで老後資金の心配のタネが和らぐ効果は間違いないし、特に医療費控除は使わないと損!
「原資をつくる=医療費控除」
「資産を守る=高額療養費制度・介護保険」
50代・60代は若者と同じ投資でいい?リスク許容度の違いを見極めよう
若い世代は投資期間が長いから、多少の値動きも時間で吸収できる。
でも、50代・60代は「退職」「年金」「生活設計」がリアルに近づく世代。
同じようにリスクを取ればいいわけじゃなく、自分に合った戦略が必要になる。
ポイントはこの3つ。
- 安定収入を武器に、余裕資金を運用
現役世代のうちは給与収入があるから、投資にまわせる「余裕資金」を確保しやすい。ここを上手く活かすのがカギ。 - 生活防衛資金を死守しつつ、攻める部分を決める
病気や介護、急な出費にも耐えられる資金は必ず確保。その上で「攻め」に使える資金をどれだけ作れるかが勝負。 - 経験を活かして、冷静にリスクを判断する
過去の投資経験や景気変動を体験してきたからこそ、若い人より落ち着いて判断できる。数字の上下に振り回されない強みを活かそう。



でもさ、この年代になると退職も近いし、守りすぎても老後資金は増えない気がするんだけど…。



全然そんな事は無いよ。
守りと攻めのバランスを自分仕様に調整するのは大事なこと。生活防衛資金を確保しつつ、余裕資金はしっかり投資に活かす。これがつむぎ流、50代・60代の戦い方。
iDeCoで老後資金を固める!50代・60代のつむぎ流逆転資産形成
50代・60代になると、「もう資産形成は間に合わないかも…」って思う人もいるかもしれない。でも、この年代だからこそ効率的に老後資金を作れるポイントがある。
時間は若い世代ほど長くはないけど、収入や経験、そして国の制度をうまく活用すれば、短期間でも資産を増やすチャンスは十分にある。
ここでは、まずiDeCoを使った資産形成の第一歩から見ていこう。
50代・60代の資産形成はまず「iDeCoからスタート」
50代・60代から老後資金を作るなら、最初の一歩はやっぱりiDeCo(個人型確定拠出年金)からがおススメ!
なぜかというと、この年代には「時間は少ないけど資産を増やす土台が作りやすい」という特徴があるからなんだよね。
まずは国の制度をフル活用して原資作りからスタートしよう。
iDeCoから始める最大の理由は、NISAには無い最大のメリットである所得税・住民税の控除が受けられるってところにある。
これはiDeCoに拠出する金額が大きければ大きいほど、控除も受けられるから、ここで浮いた資金を原資に再投資で複利効果を狙うって戦略♪
それにiDeCoは毎月一定額を積み立てる強制貯蓄で、老後資金の土台を作るにはもってこい。しかも掛け金が所得控除の対象になるから、節税効果もバッチリ。



そっか、iDeCoは年金要素もあるけど、所得税や住民税の控除があるから、節税で手元資金を増やすってイメージかあ。



さらに、iDeCoで土台を固めながら、節税で生まれた余剰資金はNISAの投資枠で運用するのがおすすめ。
iDeCoは守りの投資、
NISAは攻めの投資って感じかな。
両方を上手に組み合わせることで、短期間でも資産を効率的に増やす戦略が作れるってこと。
それに投資期間が限られている世代だから、iDeCoの強制貯蓄のロック期間は資産形成にはもってこいの制度。
これで一時の感情で資金に手を付けることなく老後資金を作れるよ。
これが、つむぎ流スパルタ式資金形成術♪
iDeCoを活用して老後資金を効率的に増やす方法
iDeCoは「老後資金の土台」を作るための強力なツール。
単なる節税制度としてではなく、控除を活用して生まれた資金を再投資に回すことで、資産形成のスピードをぐっと上げることができる。
① 節税メリットを最大化する戦略
iDeCoの最大の魅力は、掛け金が全額所得控除の対象になること。
これにより、所得税・住民税が減り、手元に残るお金を増やせるよ。これはiDeCoだけにある控除制度。
50代・60代は、若い世代と比べて、ある程度所得がある世代だから、掛け金をフル活用するほど節税効果も大きくなるのがポイント。



どれくらい控除を受けられるの?



例えば、企業年金がない自営業の場合だと、50代・60代は最大月68,000円まで掛けられる。
年間だと 68,000円 × 12か月 = 816,000円。これがそのまま所得控除の対象。
- 所得税率20%なら:
816,000円 × 20% ≒ 163,000円 の節税 - 住民税率10%なら:
816,000円 × 10% ≒ 81,600円 の節税
つまり、合計で約 24万円分の手元資金を増やせる計算になるよ。
コレ、馬鹿に出来ない金額だよね



なるほど!控除で得たお金をそのまま投資に回せるってことか。



50代・60代ともに控除の仕組みは同じ。
節税効果も十分出るよ。
② 控除で得た資金を再投資の原資に回す
節税で浮いたお金はそのまま投資の原資に回すのがつむぎ流。
「節税+再投資」の好循環を作ることで、資産形成の効率を高められる。



節税で浮いたお金は、そのままNISAや他の運用に回すのがコツ。



なるほど、税金分を原資にしてさらに資産を増やすってことだね。
③ 複利効果を活かした資産形成のコツ
iDeCoは運用益も非課税。
つまり、長く運用するほど複利効果が資産を押し上げる。
たとえ50代からでも、10年~15年の運用期間があれば、元本を着実に増やすことが可能。
50代から始める場合:
拠出期間は10〜15年ほどあるので、元本+運用益の複利効果で資産を着実に増やせる
60代から始める場合:
拠出可能期間は65歳までなので運用期間は短め。元本中心でリスクを抑えた運用が現実的ではあるけど、拠出額を活かして節税で生まれた原資を再投資へ回すことで資産を増やせる。再投資にはNISAがおススメ♪
50代・60代とも、iDeCoで元本リスクを抑えた守りの投資が基本戦略!



なるほど、年齢によって戦略も変わるんだね。



そう。iDeCoは年齢に応じて運用手法を工夫すれば、50代・60代でも十分メリットがあるんだよ。
50代と60代で変わるiDeCo戦略のポイント
iDeCoは 「始める時期」で運用スタイルがガラッと変わってくる。50代と60代、それぞれの戦略を見ていこう。
50代スタートは投資期間を活かしてバランス運用



50代から始めても、ちゃんと増やせるの?



もちろん。50代なら60歳まであと10年、65歳までなら15年運用できる。複利効果を活かすには十分な期間だよ。
- 元本保証型(定期預金・保険)だけじゃなく、投資信託を組み合わせる
- 株式インデックスファンド:債券や定期預金=7:3 くらいのバランスで、リスクを抑えつつリターンを狙う
- 拠出した掛け金は全額控除なので、節税効果で実質利回りもアップ



なるほど、攻めと守りをミックスするってことか。
60代スタートは短期でも効率的に資産形成



じゃあ、60代から始める人はどうすればいい?



60代は運用できる期間が短いから、基本は「元本重視+控除メリット活用」が軸になるよ。
- 65歳までが掛け金の上限なので、実際の運用は数年~5年程度
- この期間では大きなリスク資産に偏ると回復が間に合わない可能性あり
- 基本は元本保証型をベースに、少しだけ株式や債券を組み合わせる程度でOK
- ポイントは「節税メリットを確実に得て、その浮いた分を他の投資(NISAなど)に回す」こと



なるほど、60代は「守りながら節税メリットを活かす」ってことか。



そうだね。短期間でも控除効果で手取りを増やせるから、効率的に資産形成につながるんだよ。
iDeCoのメリット・デメリットを押さえて賢く運用
iDeCoは節税メリットが大きい一方で、いくつかの制約や注意点もある。両方を理解しておくことで、無理なく賢い資産形成ができるよ。
拠出可能期間と掛け金の目安



iDeCoって、何歳まで積み立てられるの?



原則は65歳まで。
50代からでも約10〜15年、
60代なら数年だけど、それでも節税メリットは大きいよ。
- 掛け金の上限は職業・加入状況で変わる
・会社員(企業年金なし):
月額23,000円
→ 改正後:月額62,000円
・会社員(企業年金あり):
月額12,000〜20,000円程度
→ 改正後:月額62,000円
・自営業:
月額68,000円
→ 改正後:月額75,000円 - 無理なく続けるなら「毎月2〜3万円」が現実的ライン



上限までいかなくても、少しずつ積み立てるだけで節税になるんだね。
注意点やデメリットも理解して活用
もちろん、いいことばかりじゃないから、ここは押さえておこう。
- 60歳まで引き出せない
急な出費には使えないから、生活資金は別に確保しておく必要あり。 - 運用商品に元本割れリスクがある
投資信託を選ぶと増える可能性もあるけど、逆に減るリスクもゼロじゃない。 - 受け取り時に課税ルールがある
一時金なら退職所得控除、年金形式なら公的年金控除の対象になる。
退職金との受け取りタイミングによっては課税が増えることもある。



そうかあ、節税メリットは大きいけど、制約もちゃんと理解しておかないとね。



そうそう。メリットとデメリットを両方知って、ライフプランに合わせて使うのが「つむぎ流の賢いiDeCo活用法」
iDeCoは「節税しながら老後資金を固める」50代・60代の強力カード



ここまで聞いて、iDeCoってやっぱりすごいね。



そうだね。 改めてポイントを整理すると、50代・60代からでも十分活用できる制度だって分かるよ。
iDeCoの最大メリットは「節税効果」
掛け金が全額所得控除になるから、毎年の住民税・所得税が軽くなる。
実質的に「国からの還元」を受けつつ投資ができるのは、大きな魅力♪
強制的に積み立てられる安心感



自分で貯金だと、つい使っちゃいそう…。



その点、iDeCoは「60歳まで引き出せない」仕組みだから、半強制的に老後資金が積み上がるよ。
これはデメリットでもあるけど、50代・60代からはむしろ「確実に資産を残す仕組み」としてプラスに働く!
デメリットも理解して賢く利用
- 流動性の低さ(60歳まで引き出せない)
- 投資信託では元本割れリスクあり
- 受け取り時は退職金や年金と合算して課税
こうした制約を知ったうえで、ライフプランと重ならないように設計することが大切。
50代・60代のiDeCo控除シミュレーション(会社員・掛け金少なめパターン)
① 50代から始める場合(15年想定)
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 掛け金上限 | 月2.3万円/年27.6万円 |
| 年収 | 600万円(仮定) |
| 所得税率 | 20% |
| 住民税率 | 10% |
| 15年での拠出金額 | 414万円 |
| 節税金額 | 124.2万円 |
シミュレーション結果:
節税で浮いた124.2万円を再投資に回すことで、複利効果も加わり資産形成を加速
② 60代から始める場合(5年想定)
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 掛け金上限 | 月2.3万円/年27.6万円 |
| 年収 | 600万円(仮定) |
| 所得税率 | 20% |
| 住民税率 | 10% |
| 5年での拠出金額 | 138万円 |
| 節税金額 | 41.4万円 |
シミュレーション結果:
投資期間が短いため、資産運用はリスク控えめにする。
・債券・定期預金など安定資産中心
・節税で浮いたお金を再投資原資に活用
複利効果は短期間でも少額積み重ねで資産形成に寄与
iDeCoで守りの資産形成を固めたら、NISAで攻めの資産形成へ
50代・60代の老後資金づくりでは、まずiDeCoで節税しながらの強制積立で資産の土台を固めることが基本戦略。
iDeCoで「守り」を固めたら、次はこの資金をさらに成長させる「攻めの資産運用」がポイント。この複利効果を狙った合わせ技として活用できるのが次のセクションで紹介するNISAだよ。
NISAで伸ばす!50代・60代の余裕資金を活かすつむぎ流資産形成戦略
つむぎ流・50代60代のための資産形成術では、NISAとiDeCoをこう整理してるよ。
- iDeCo=守りの資産形成
所得税・住民税の控除を受けながら、老後資金をじっくり積み立てる。確実に“土台”を固める役割。 - NISA=攻めの資産形成
iDeCoで節税して浮いた原資を、NISAで再投資。複利効果を最大化して“攻め”の成長を狙う。
この二つをどう組み合わせるかで、50代・60代からでも資産形成のスピードと安心感が大きく変わってくるよ。
それじゃあ次に、攻めの要となる「NISA」の戦略を見ていこう。
NISAは「攻めの資産形成」。iDeCoとの違いを押さえる
50代・60代の資産形成で、iDeCoとNISAは役割がまったく違う。
まず、iDeCoは「守りの資産形成」。
所得税・住民税の控除を受けながら、老後資金をじっくり積み立てる。これで確実に土台を固めることができるよ。
一方、NISAは「攻めの資産形成」。
iDeCoで節税して生み出した原資を使い、非課税枠の中で再投資することで、資産を増やすチャンスを狙う。
ポイントは、この二つの組み合わせ。
守りのiDeCoで安定を確保して、攻めのNISAで複利効果を最大化して資産形成を加速!
これがつむぎ流の50代・60代向け基本戦略♪



iDeCoは安全重視で、NISAは攻めるための資金を作る感じなんだね。



そう。まず土台を固めて、そこからの余裕資金をNISAで運用するのが、つむぎ流の基本的考え方。
非課税枠をどう活かす?つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
新NISAの非課税枠は年間360万円、最大で生涯1800万円まで。
50代・60代の場合、一気に全額を使う必要はなく、余裕資金に応じて配分するのが基本。
つみたて投資枠は、安定的な長期運用向け。
- 投資対象は、インデックス型の投資信託や、パフォーマンスの良いETFなどが中心。
- 毎月一定額を積み立てることで、価格変動リスクを平均化しつつ、生活防衛資金を圧迫せずに運用できる。
一方、成長投資枠は、株やETFで攻めの投資を狙う部分。
- 投資対象は、業績が安定している個別成長株や、幅広く分散された成長ETF。
- 50代・60代は投資期間が短めのため、少額・分散投資でリスクを抑えつつ、複利効果や成長性を活かすのがポイント。



非課税枠をどう割り振るか迷うなぁ。



無理して全額使う必要はないよ。つみたて枠で安定を確保しつつ、成長枠で少し挑戦するくらいが50代・60代にはちょうどいいくらい。
ポイントは、つみたて投資枠と成長投資枠のバランスと投資対象の選び方。
- つみたて枠:インデックス型投信やETFでコツコツ安定運用
- 成長枠:成長株や成長ETFで攻める少額投資
まず土台を守るつみたて枠、そして余裕資金で攻める成長枠を少しずつ活用するのが基本戦略だよ。
短期売買は不向き?長期投資で非課税メリットを最大化
NISAは非課税で運用益を積み上げられる制度だけど、短期売買にはあまり向かない。
その理由はシンプルで、頻繁に売買すると非課税の恩恵を十分に活かせないから。
長期投資の強みはここにあるよ。
- 短期の値動きに左右されない
- ドル・コスト平均法でリスク分散できる
- 複利効果を時間をかけて最大化できる



でも、株価が下がったら、ちょっと怖いよね…。



確かに一時的な下落はあるけど、長期で積み立てることで価格変動の波を平均化できるのがポイント。
焦らず続ければ、非課税メリットも最大限活かせるのがNISAの魅力だよ。
ドル・コスト平均法とは:
毎月一定額を投資することで、価格変動の波を平均化する手法のこと。
これにより、高値掴みを避けつつ長期で安定した資産形成が可能になるよ。
ドル・コスト平均法のイメージ
毎月一定額を投資すると、株価が高い月は少なめ、株価が安い月は多めに買うことになるよ。
結果、購入単価を平均化してリスクを分散できるってこと。
- 1月:株価1000円
→ 1万円で10株購入- 2月:株価800円
→ 1万円で12.5株購入- 3月:株価1200円
→ 1万円で8.3株購入合計 30.83株 / 総投資額 3万円
→ 平均購入単価 973円



でも、どの銘柄に投資するか迷うなあ…。



50代・60代のNISA投資では、テクニカル分析よりもファンダメンタルズ分析が向いているよ。
具体的には、企業の業績や財務状況、成長性、業界動向などを見て、安定的かつ成長が見込める銘柄を選ぶのがコツ。
だから、つみたて枠で安定的なETFや投資信託、成長株枠で業績の良い個別株を分散投資するのがつむぎ流。
毎月の一定リズムで投資しながら、非課税メリットと複利効果を最大化していこう。
つむぎ流資産形成術!iDeCo+NISAで回す長期投資
50代・60代の資産形成では、守りのiDeCoと攻めのNISAをセットで運用するのがつむぎ流スタイル。
基本の考え方はシンプルだよ。
- iDeCoで節税しながら老後資金を土台として積み立てる
所得税・住民税の控除で得た分は、生活に影響を与えず資産を積み増す原資になる。 - 浮いた節税額や余裕資金をNISAで再投資
非課税枠を使って複利効果を最大化。
50代・60代でも効率的に資産を増やすことができる。 - トレードで得た利益もNISAへ回す“おまけ運用”
日々のスイングトレードや中期トレードで得た収益を、非課税枠に追加して運用。
守りのiDeCo+攻めのNISA+トレード利益の3つを回すことで、資産形成を加速させる。



iDeCoで土台を固めて、NISAで伸ばす感じだね。



そうそう。さらにトレードで生まれた利益をNISAに回すことで、資金を回転させながら長期運用できるのがポイントだよ。
つむぎ流スタイル!守りのiDeCo+攻めのNISA+トレード利益の三重奏♪
つむぎ流スタイルは、守りのiDeCo+攻めのNISA+トレード利益の再投資という3段階の仕組みで資産を回す長期投資術。
① iDeCoで土台を固める
- 掛け金上限:月2.3万円(会社員の場合)
- 年額拠出金:27.6万円
- 想定投資期間:50代なら15年、60代なら5年
- 節税メリット:所得税+住民税で30%控除
- シミュレーション(50代)
- 拠出総額:27.6万円 × 15年 = 414万円
- 節税額:414万円 × 30% ≒ 124.2万円
- 節税で浮いた124.2万円はNISAや追加投資の原資に
② NISAで余裕資金を伸ばす
- 非課税枠:年間360万円・生涯1800万円
- 投資先の例
- つみたてNISA:長期安定型ETFや投資信託
- 成長株NISA:業績の良い個別株や成長ETF
- 運用のポイント
- 長期投資で非課税効果を最大化
- ドルコスト法で毎月一定額を投資し、価格変動リスクを分散
- ファンダメンタルズ分析をベースに銘柄を選定
③ トレード利益もNISAに回す(おまけ)
- 日々のスイングトレードや中期トレードで得た利益を、非課税枠に追加
- iDeCoで土台を固め、NISAで余裕資金を伸ばしつつ、さらにトレード利益を活用
- 資金を循環させながら複利効果を最大化



iDeCoで守り、
NISAで攻め、
さらにトレードで稼いだ分も回す…
まさに3段構えだね。



こうすることで50代・60代でも効率よく資産を増やせるよ。基本は順番が大事!
〖まとめ〗iDeCoで固め、NISAで伸ばす!50代・60代の逆転資産形成
50代・60代からの資産形成でも、順序を意識すれば逆転は十分可能。ここまで解説したiDeCoとNISAの活用法を整理して、つむぎ流の“守りと攻めの資産形成術”を振り返ろう。
iDeCoは「強制貯蓄+節税」で老後資金の土台を築く
まずは守りのiDeCoで土台作り。
所得税・住民税の控除を受けながら老後資金をコツコツ積み立てることで、確実に資産の基礎を固められるよ。
50代・60代からでも、この土台があるのとないのとでは安心感が大違い。
NISAは「自由度+成長性」で余剰資金を運用
次は攻めのNISA。
iDeCoで節税して生み出した原資や、トレードで得た利益を非課税枠に回すことで、資産の成長スピードを加速させられる。
守りの土台があるから、NISAで多少リスクを取った運用にも安心して挑戦できるんだよ。
50代・60代からでも遅くない!逆転資産形成は“順番”がカギ
つむぎ流では、資産形成の順番がとっても大事。
「守りのiDeCo → 攻めのNISA → トレード利益の追加投資」 の順で資金を回すことで、50代・60代からでも効率よく資産を増やせるよ。順序を意識するだけで、焦らず安全に逆転形成を狙える!
年齢を重ねてからの資産形成でも、焦らず、順番を守り、複利効果を最大化することが逆転への近道。
守りと攻めを組み合わせたつむぎ流戦略で、安心と成長の両方を手に入れよう。
ここまで読んでくれて、ありがとう!
当ブログ「つむトレ」では、株式投資やトレードにかかわる情報をいろいろ配信していきます。
また遊びに来て下さいね♪



では次の配信をお楽しみに♪
風雅なスイング投資家のつむぎでした!



まったね~♫ ♪
\ 合わせて読みたい /